成相寺の光と影
先日、初めて宮津の成相寺に行ってきました。
寺伝によれば慶雲元年(704)真応上人の開山、文武天皇の勅願所と言われています。
歴史の古い寺です。今でこそ西国28番札所として観光客で賑わっておりますが
元々はこれどころではないもっともっと栄華を誇っていたのです。
成相寺に行く参道の脇には『本堂跡地』『五重塔跡地』など跡地に
看板が建てられています。今の規模に比べてもっともっと大きな寺院だったんです。
それを表しているのが成相寺参詣曼荼羅

(Wikipedia:成相寺よりお借りしています)
今の規模とは全然異なり、栄華を誇っていたのです。しかし、戦国期の戦火に
巻き込まれ幾度と無く再興はされるものの江戸期には衰勢の一途で現在は
本堂・地蔵堂・鐘楼・奥の院慈眼堂・仁王門・宝蔵・鎮守堂残すのみとなりました。
成相寺の山頂展望台に行くまでに戦火の傷跡が残っています。
この山からはたくさんの地蔵が出てきてます。(写真は展望台手前)
その地蔵が集められてるのが宮津市難波野の千体地蔵。
ここに集められています。丹哥府志によると成相山から出たもので大半のものが
室町期から近世初期のもこの間に戦国期も含まれます。恐らく、これは戦火で命を
落とした兵士を供養したものではないのか?
成相寺は南北朝時代・戦国期には激しい合戦地であり成相寺が城の役目を
果たしていたようだ(成相寺城という城も合ったようです)そして周囲には
今熊野城・府中城・阿弥陀ケ峰城と城があり、成相寺からは天橋立が一望できる
とても良い軍事拠点にもなりうる場所です。
戦国期には守護一色家(一色義有)の力が弱まると丹後守護代延永春信、有力国人衆石川直経の
内紛が勃発。その隙を付いて元々仲の悪い若狭の武田元信、管領家細川政元が加わり、
この地で大合戦が。府中城とこの成相寺が武田元信に取られてしまいます。。。
その時になんと・・・一色義有は夜襲をかけ成相寺に火を放ったのです。武田勢は総崩れで
武田元信は命からがら若狭へ戻ったそうです。その時に成相寺と寺を元に戻すという
約束が成されており一色氏の手により再建されているようです。
雪舟が天橋立図描いてしばらくして成相寺は戦火により焼け
小京都と呼ばれた府中も…。栄華を誇った最後の時を知る事のできる貴重な絵です。
京都府宮津市成相寺339 西国第二十八番札所成相山成相寺
![]() 最後までご愛読ありがとうございます。宜しければクリックをお願い致します
最後までご愛読ありがとうございます。宜しければクリックをお願い致します
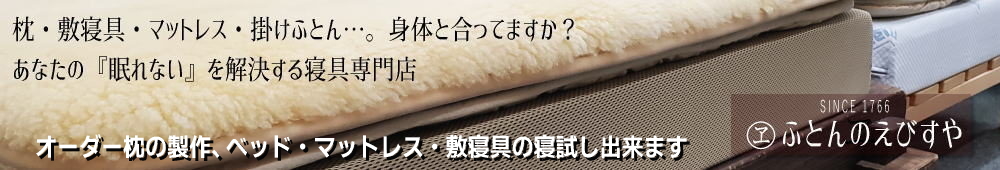























宮津からケーブルで傘松までは行った事あるんですが、まださらに山のうえにあるんですね、そんな場所に千体地蔵あるんですね~
いげのやまさん
傘松とはまた別ルートでバスも出ています。もっと高い位置になりますね(^^)
千体地蔵の場所は籠神社の裏手の方になりまた成相山から離れた場所にあるんです。
成相寺にそんな壮絶な歴史があったなんて…
千体地蔵の写真もインパクトありますね。
こんな引き込まれるような記事を書けるゑびすやさん、
本当に尊敬します。
丹後のヨメさん
嬉しいお言葉有難うございます。詳しい方の受け売りや
ネットなどで調べたりしていますので僕自身はたいして
詳しくありませんが好きなんですね(^^;書くことで
ちょっとずつ頭に入ってきてるんかな?と思います。
丹後には丹後の奥深い歴史がありますので皆さんが
興味を持ってくれると嬉しいです